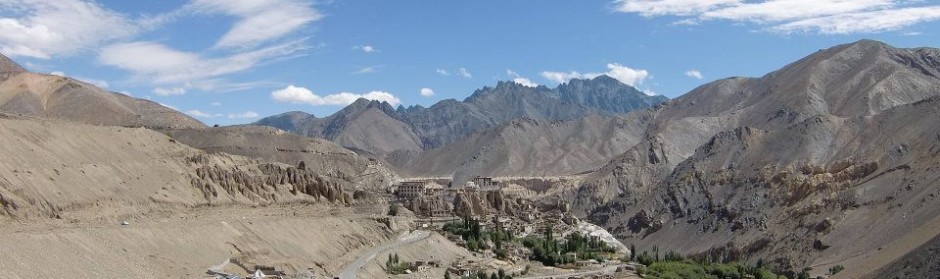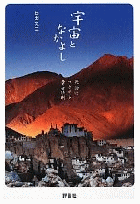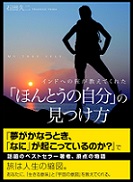マーケッターとして数々の企業を救ってきた神田昌典氏であるが、本書は冒頭でショッキングな報告から始まる。癌告知を受け、生きるか死ぬかの境に身を置いていたのこと。幸いにも今は克服したからこそ、このように新刊を出せたのであろうが、そんな背景があったためか、これまでのマーケティング本や小説、さらにはスピリチュアル本とも随分異なった印象を受けた。
と言っても話の内容は、ここ数年、著者が主張していたこととそう変わらない。つまり世の中を俯瞰的に見たとき、歴史には70年のサイクルがあるとの説がベースになっていること。それに従うと、今の日本はちょうど70年前の太平洋戦争終戦、そしてさらにその70年前の明治維新に匹敵するサイクルがやってきているとのこと。その変化は10年のうちに劇的にやってくる。それが2022年に向けたこれから10年、活躍できる人の条件と言うわけだ。
結論から言うと、著者は日本のこれから10年に対して、かなり楽観的な見解を示している。しかし、一般的にはエコノミストを中心にかなり悲観的な意見の方が目立っている。1990年辺りまでは、資源がないながらも圧倒的な内需拡大によって、ナンバーワンと呼ばれるほどの経済成長を遂げてきた日本だが、バブル崩壊以降は減速の一途をたどっており、さらには中国や韓国の追撃をくらいながら、国際競争力も弱まるばかりである。さらにこれからは高齢化による社会経済の停滞も避けられないところにある。
そのようなマイナス要因が重なりながらも「楽観論」を展開するのは、死を間近に見た開き直りかもしれない。もちろん良い意味で。ただ、私個人としては本書を読んでかなり勇気づけられたり、モチベーションも上がってきた。しかしそれは、私自身が本書の主張する楽観論にたまたま当てはまっている状況だからかもしれず、そうでない大多数の人たちにとっては手痛い内容かもしれない。
その手痛い当事者となるのは「会社」という従来の組織の枠組みで生きてきた人たちである。なぜなら著者は、今から12年後には「会社」がなくなると予想しているからだ。そもそも「会社」の役割とは何か。それは「取引費用」の軽減にあるとされる。簡単に言えば、一人一人が完全に独立した就業形態だと、技術や情報の蓄積、契約、営業、経理、税務、人材育成などに多くの「無駄」が生じるからである。しかし一方で、組織が大きくなればなるほど意志決定に時間がかかるなど硬直化が進み、イノベーションの勢いが減速するなどのデメリットもある。
しかし今の日本の現状を見ると、終身雇用や年功序列の神話化が進む現状で、若い人たちが一つの会社に留まっている必然性は薄れている。そのため外部市場経済が活性化し、技術や人材の蓄積へのモチベーションの低下が進んでいる。現に大企業からの、中国や韓国への技術流出が問題となっているではないか。さらにインターネットによって、情報そのものの価値が低くなり、企業が情報を持つだけでは成り立たなくなっている。また、インターネットは様々な事務コストを軽減するため、「会社」でコストを受け持つ意義も小さくなっている。
従って、今後はもちろん「器」としての会社は残るであろうが、就業形態はよりノマド化し、一人一人のネットワーク力、発信力が重要になってくるのである。そのような時代において、著者は次の3つの能力・体験を重要視する。
1.英語力、中国語力
2.ボランティア体験
3.優秀な人材のいる場所にいること
1の英語力・中国語力については、内需中心の時代にはさほど必要じゃなかったかもしれないが、今後はそうもいかない。しかし、重要なのはネイティブ並の会話力ではなく、仕事に使える力でいいので、その気になったらいつでも学べる。2のボランティア体験は痛みを知る上でも重要なこと。その痛みを知ることで強くなるのだから。3についてはなるべく若い時期から優秀な人たちを見ることで、セルフイメージも引き上げられる。
では、そう若くない人はどうすればいいのか。タクシー運転手を見ると、実は日本ほど知的教養レベル、経験レベルの高い人材が集まっている国も少ないと言う。つまり、高い技術や経験を持ちながら、会社の体力低下によってやむなくリストラされ、行くところがなく運転手になっている人も現実にいるし、それはもちろん運転手に限ったことではないだろう。もし、その人たちが事業の立ち上げ方を知っていたら、ものすごいことになっていた可能性は高い。
そして今、間違いなく時代はシフトしており、著者が言うには、以前ならば松下幸之助であっても乾電池や電球は売れなかったが、今なら視点を変えれば売れるではないか、と。漬け物石だって、以前は絶対に売れないと思っていたが、工夫次第では売れる時代になっている。時代が動く時期、それまであった商品とそのニーズとの間にはギャップが生じるが、そのギャップを埋めるようなアイデアを出せば、何だって売れるようになるのだ。
つまり、リストラにあった年輩の人たちだって、やり方さえわかればライフワークに身を投じ、豊かな後世を送ることだってできる。そのために必要なことは、経営者や起業家が集まる「場(コミュニティ)」にいるかどうか。「会社」という枠組みだけでライフプランを考えるのではなく、個人としてのネットワーク力、発信力を高めていけば、様々な形で価値を創出することができるのだ。そして著者は、今を「人類史上最も簡単に起業できる時代」だと言う。
それを聞いて、確かにその通りだと思った。私自身、何もない状態から独立して7年間、曲がりなりにもやってこれたのは、自分の実力では決してない。時代があったからである。実のところ、インターネットがなかったら、ブログがなかったら独立なんてできないでしょ、と揶揄されたことはあるが、それは言っても始まらない。今に生きている以上、条件は同じだからだ。もし今、高校を卒業したばかりの経験も何もない普通の青年が、今の時代の知識を持ったままタイムマシンで100年前の日本に行ったとしたら、誰だって歴史に名を残すであろう。しかし現時には不可能。つまり、今の時代にどのように生きるかだけが重要であり、その意味で言うと「人類史上最も起業しやすい時代」に生きているからこそ、起業できただけのことである。
本書のベースにあるのは70年サイクル説によって時代を俯瞰する視点。その点では、確かに今、激怒の時代に向かおうとしているのは確か。しかしどのような時代においても、そしてどの国(先進国)に生きていたとしても、「絶対的」な絶望はあり得ない。大切なのは「視点」である。これはもちろん起業するのがよくて、サラリーマンがダメと言ってるのではない。どの立場におかれようと、「視点」によって状況が180度変わることを言っているに過ぎない。
つまり本書の最大の読みどころは、将来予想とか、どうすれば儲かるかって話ではなく、どのような「視点」を今後持つべきかということであろう。私はそのように読んで、今、ずいぶんとモチベーションが上がってきているのは確かなことだ。
2022―これから10年、活躍できる人の条件 (PHPビジネス新書)/神田 昌典

¥882
Amazon.co.jp
<追記>
ただし、星をつけるならば多くて三つかな。「優しい会社」も同じような結論だったけど、2015年以降の予想だにできない時代予想が「SNS」と「NPO」に落ち着いているところが、神田さんとて限界かなと感じます。NPOはドラッガーがすでに言ってることで新鮮味もないし、SNSは今の流れを踏襲しているだけ。なので「予想」としてはまったく目新しいものはないですが、世の中を俯瞰的に見る練習にはいいかな、と思いました。
人生を変える100日ブログ:67日目