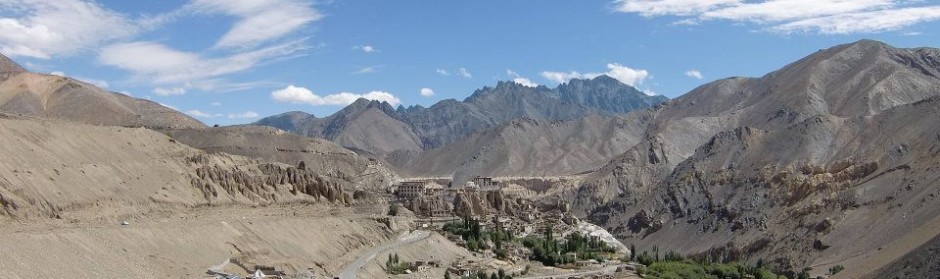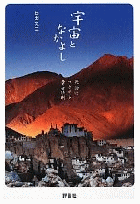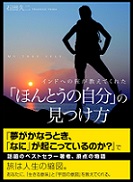元々仏教とは縁もゆかりもない生命科学者による「般若心経」の訳本。本書を手に取る前、NHKの「ラジオ深夜便」のCDシリーズ「生命科学で読み解く般若心経」を何度も聞いていた。著者の肉声により語られる般若心経論に感動を覚えたものだ。著者は極めて優秀な生命科学者であったが、若き日に原因不明の難病に襲われ、以来、人生の半分以上は闘病生活である。
あまりの苦しさから何度も死のうと思ったそうだが、結局、思い切ることもできず宗教に救いを求めようとする。とりあえず仏教に馴染みを感じ、仏教に関する本を読んでいたのだが、その折り、いよいよ職場から解雇され、我が子を失うかのような悲しみに突き落とされた。その晩、夜が明けようとしたとき、突然、著書に「神秘体験」が訪れた。炎に包まれ、目の前の一本の道ができ、もう大丈夫と悟った。そして何とも言えない幸せに包まれたと言う。
このような「体験」は実はさほど珍しいことではない。同じような、それも驚くほどに似たような「体験」をしている人がいる。その瞬間にすべてを悟ってしまう。そのすべてとはまさに「空」への悟りであろう。
著者は元々は自然科学の研究者であったが、実はお釈迦様も自然科学的な知識と直感により「空」の本質を直視していたのではないかと仮定する。もしかしたら、紀元前5世紀のギリシャの哲学者デモクリトスの「原始論」をお釈迦様も知った上で「空」を説いたと考えた方が、特にこの「般若心経」においては自然ではないかと言う。
本書の極めて興味深い点は、著者がまず「悟り」に対する一時体験を有し、そして自然科学的な見識と、そして歌人としての完成により「般若心経」を読み解いたことであろう。
仏教では人生の本質を「苦」と説くが、同時にその「苦」を超えることもまた仏教の指南することである。では、なぜ人は苦しむのか。著者はその根元に「自我」の存在を置く。原因不明の難病により、想像を絶する「苦」を味わい、その極限に来たとき、「悟り」は突然やったきたのだと言う。「空」とは何か。それは物質の最小単位である「原子」のこと。この世界はすべて一元的な「原子」でできており、単にその濃淡があるだけ。
実のところ「空」を「原子」に求める般若心経解釈は珍しくはない。むしろ量子力学が物理世界の前提にある今、ごく自然な感覚でとらえられる。それでもやはり本書が心に響くのは、著者の体験性によるものだろう。苦しみの原因は自我にある。これもまた仏教によらずあらゆる宗教が主張していることだが、著者は実際に「神秘体験」により自らの自我が消滅し、絶対的な至福を体験したからこそ書ける般若心経訳である。
今や般若心経に関する解説書は無数にあるが、本書が異彩を放っているのは、実際に手にとって一読すればわかるであろう。凡百の解説書よりも遙かに「空」を体験できる一冊である。
生きて死ぬ智慧/柳澤 桂子

¥1,200
Amazon.co.jp
人生を変える100日ブログ:72日目