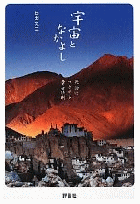控え目に告白するが、私は「官能小説」が嫌いでない。高校時代は寮生活をしていたが、男性誌として一般的だったのは、もっぱら企画ものの写真雑誌及び男性漫画雑誌であった(「男性」と言ってもサブ系ではない)。各部屋には必ず数冊あったものだが、私のロッカーに入っていたのはほとんどが官能小説であった。ただ、私自身、特に活字が好きだったわけじゃなく、実のところ高校を卒業するまで活字らしい活字はほとんど読んだことがない。例外的にはクラシック音楽に関する解説本があったくらいで、読む本はほとんどがマンガであった。もちろん写真系の男性誌も目にすることは多かったが、それ以上に官能小説を愛読していた。そしてあえて言わないでおくが、特に好きな作家もいた。好きなジャンルもあった。
しかし、当時の同級生の中には私のように「官能小説が好き」と言う人間はいなかった。いや、私も言ってなかった。となると、私のように好きだけど言わないでいた同級生も必ずいたはずだ。正直、寮生活をしていると、全員が全員ではないが、男性誌を読むこと、所持することにさしたる抵抗はない。借りることも貸すこともそうで、しばしば他の部屋の人間が「エ○本貸してくれへ~ん」と訪れることもあった。そう言いながら、勝手に机の引き出しを開けて持って行く人間もいた。しかし、「エ○小(官能小説のこと)貸してくれへ~ん」と言って入ってくる人間はいなかった。
ある時期、私の部屋には変な奴が集まっていた。坂本と倉橋という同級生などは、自分たちで官能テープ(「マド○ナメ○ト」を代表としたAV女優による吹き込みテープのこと)を自作して楽しむほどの変な性癖を持っていた。ちなみに倉橋が女役である。それがある日、私の持つ官能小説が彼らに見つかってしまった。その二人はなぜか嬉しそうに、その小説のタイトルを読み上げ、私を揶揄するのである。よりによってその二人からである。通常の男性雑誌ではそうはならない。官能小説だから、である。しかし、同じ部屋の中山はその小説をそっと取り、勉学時間に読み耽っていた。
その一連の扱われ方に、官能小説ならでは奇異性があると感じていた。なぜに、官能小説は秘められる存在なのか。ちなみに昨今、kindleやipadの登場により電子書籍が話題となっているが、実はそれ以前からずっと電子書籍で堅い市場を持つジャンルがあった。言うまでもなく官能小説である。そして通常、紙の本よりも電子書籍は安いはずなのだが、官能小説はなんと電子書籍の方が高い。それだけ電子のニーズがあると言うことは、やはり持っている、読んでいるのを知れたくないからなのか。ただ、その一方で駅のキオスクなどには堂々と売られている。ずっと昔からそうだ。あれは一体誰がいつ買うものなのか。そしてどこで読むのか。
私はキオスクでは買ったことがないし、私のない知恵から推測すれば、きっとこうであろう。人は誰もが官能小説に対する隠れたニーズを持っている。しかし、買うのはなんか恥ずかしい。コンビニで中学生が「ふたりえっち」をいそいそとレジに持って行く並に恥ずかしい。もしコンビニや書店で後ろに並ばれたりしたら、相対性理論でその時間はいつもの10倍は長く感じるだろう。しかし、キオスクは基本的に並ばない。熟練した店員だと客が品物を見せると同時にお釣りを差し出すほどのスピードだそうだ。キオスクにはコンビニと違って電子レンジもないため待つこともない。しかも最大の利点は、定員はほとんどがオバチャンであり、バイトの女子大生が入っていることなどほとんどない。しかもラッシュ時などの客はほとんどが男である。これほど官能小説を買うのに適した環境はないのではないか。なぜ、キオスクには官能小説が必ず売られているのか。それは単に「買いやすい」からであろう。読むのは駅や車内である必要もない。「買う」ためにキオスクに置かれてるのである。
それはともかく、本書の書評に入りたい。正直、ものすごくよくまとまっている。「官能小説の文体の歴史」「性器描写の工夫」「性行描写の方法」「フェティシズムの分類」「ストーリー展開の技術」など数ある官能小説をそれぞれに要素から分類、分解し、分析、解説を加えている。もちろん文章の引用も併せて。
しかしこのように並べてみると、官能小説の表現とはなんと多彩なことか。優れた作家の手に掛かると、同じ対象であっても二つとして同じ表現がない。それでいて読者に考えさせず、ストレートに状況を想起させるのである。その表現をそのまま紹介したいとろだが、かなりドギツイので、あえて単語の優しい文章を引用したい。
「内部の景色は、夕暮れの淡水湖を思わせる。肉襞の盛り上がりもあまりなく、縦長のハートを形作ったそこは、すっきりとした潔いたたずまいであった」
いや、これでもかなりドギツイ。単語の一つ一つを見ると、「肉壁」だけがちょっと引っかかる程度で、それ以外は何一つ言いにくい言葉はない。しかし、それらを並べるだけで、かくも淫靡になろうものか。ここに文脈が入ると、私の目の前には完全に3D動画が広がってしまうではないか。
官能小説の作家たちの表現力は底なしである。ただ、よくよく考えると、日本の古典文学の最高傑作の一つである「源氏物語」などは、実際は完全なる官能小説である。また、現在日本で最もノーベル文学賞に近いと言われる村上春樹なども、ときとして意味不明なまでに官能的な描写が登場する。人間の三大欲求である食欲、睡眠欲、性欲のうち、最も動的な欲は性欲である。寝たくなるような表現は必要ない。食べたくなる表現は空腹時にはたまらないが満腹時は辟易する。しかし、やりたくなる表現は満たされた直後であっても、表現次第で瞬く間に復活させる力がある。つまり文学表現の真価とは、官能表現にありきと言ってもいいのではないか。
本書の巻末には「官能小説の書き方十箇条」なる章があるが、これが圧巻である。特に「第七条 恥ずかしいと思うな」では羞恥心を一切捨てて一つの表現・描写にぶつけろと指南する。そして何より「第十条 書いてる途中でオ○ニーするな」は思わず笑ってしまったがその通りである。プロの作家でも書きながら興奮することがあるらしい。そもそも自分が興奮せずして読者を興奮させることはできない。そこでいきおい、思わずベルトに手をかけてしまえば、それまでの興奮はやみ、そのまま文章にも反映されてしまうそうだ。途端に力のない萎れたストーリー展開となってしまう。
昨今、ブログやSNSなど個人が文章を発信する機会が増えてきた。もちろん発信する内容が第一ではあるが、表現方法が拙いばかりに、せっかくの内容が伝わらないことだってあるだろう。逆に内容は大したことないのだが、思わず読んでしまう文章にであることもある。いずれにせよ文章表現を磨くことは、読ませる文章を書く上で不可欠である。そのような文章に必ずあるのは、文そのものの色気である。この色気は、人間の性に無関係とは必ずしも言えない。もちろん誰もかれにも勃起させる文章を書くことは求められないが、色気ある文章を書く上で、そのような基礎体力は必要ではないかと思う。思えばここ数年、官能小説をまともに読んでいない。自分の文章を匂い立たせるために、再び官能小説にハマってかと思う年頃である。
官能小説の奥義 (集英社新書)/永田 守弘

¥720
Amazon.co.jp
人生を変える100日ブログ:74日目