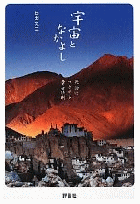バックパッカー本の元祖。
まだ日本が旅行自由化されておらず、欧米と比べて「貧乏国」として認識されていた1960年前後の旅行記。
東大生でフルブライト留学生の小田実は、言わばエリートである。
エリートの留学記かと思えば、それはアメリカでの一部のみで、今以上の、否、今とは比べものにならない程の貧乏旅行である。
しかしそれは当時の「インテリ」の書く文章。面白くないはずはなく、その面白さは今でもまったく色あせることはない。
非常に魅力的な一文から始まる。
「ひとつ、アメリカに行ってやろう、と私は思った。三年前の秋のことである。理由はしごく簡単であった。私はアメリカを見たくなったのである。要するに、たったそれだけのことであった。」
本書は単なる旅行記ではなく、小田実の当時の若い感性が、まさしく「何でも見てやろう」と世界を見て感じた「比較文化論」である。
アメリカを皮切りにヨーロッパ、中東、アジアと東向きに世界を一周するのだが、日本の位置づけの変化が非常に興味深い。
アメリカ滞在中はアメリカという富める国に対する貧乏国日本という図式が最初あったのだが、黒人という存在を定位すると、日本はすでにアメリカと同様の「西洋」に属することが浮き彫りになる。
つまり「西洋対非西洋」という図式において、日本はすでに「西洋」に属するという時代感覚が当時から既にあったことがうかがえる。
それはヨーロッパにおいても同じである。日本は「西洋」という見方の中で、単に「ZEN」という画一的なアイデンティティが与えられていたことが分かる。
現在の日本は世界先端の工業大国として確固たる地位があるが、当時は「ZEN」に代表される文化大国であったことが、小田の肌感覚として伝えられる。
つまり本書は文字通り足で見て歩いた「比較文化論」であると同時に、現代的視点から見ると、「比較世代論」であるとも言える。
終盤は圧巻である。日本は確かに「西洋」に中では貧乏国であったかもしれないが、東に進むにつれて、「貧乏」という言葉では生ぬるい程の「絶対的貧乏」と遭遇する。
とりあわけインドのカルカッタでは、所持金がほとんどなくなり、不可触民さながらの路上生活を体験する。
そこで得た経験が、後の小田の極左思想に発展するであろうことは想像に難しくない。
本書は今後も日本を相対化する比較文化論として、単なる旅行記を超えた名著となって読まれ続ける価値がある。
- 何でも見てやろう (講談社文庫 お 3-5)/小田 実

- ¥770
- Amazon.co.jp