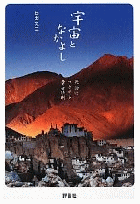- 私ごとであるが、私は高校を卒業するまでほとんど活字を読んだことがなかった。読書に疎い少年時代を過ごしてきたのである。
それが、浪人中にあるきっかけで、一夜にして読書家になり、中でも哲学書をよく読んだ。竹田青嗣氏による「現象学入門」もちょうどその頃に読んだものだ。
「現象学」は哲学の中でも、とにかく用語が難しい。現象学的還元、エポケー、ノエシス・ノエマ、間主観性、生活世界、などなど日常でお目にかからない言葉が目白押しで、「生活世界」など何となくわかりそうなものも、現象学の文脈ではさっぱりわからなくなる。
それまで活字を読んだことのない人間が、突然、むさぼるように「現象学」にかじりついたのだから、当時の私はドンキホーテそのものだった。しかし、竹田氏による本書はとてもわかりやすい。
その後、「現象学講義」「デカルト的省察」「ヨーロッパ諸学の危機と・・」などから、ハイデッガーの「存在と時間」、メルロポンティの「知覚の現象学」などを読み進める上で非常に参考になった。
竹田流の比喩もわかりやすいし、巻末の用語集もかなり使える。
たとえば「現象学的還元」を行う際、それをデカルトの「方法的懐疑」となぞらえて説明するのであるが、それを「玉ねぎの皮むき」に喩えて説明する。
デカルトの場合は玉ねぎを最後までむくとそこに芯のようなものが残り(ほんとか?)、それを「我思う(コギト)」としたのであるが、デカルトの場合はそれはあくまで「実体」としてとらえられる。
それに対してフッサールの場合は、その芯のようなものを「実体」ではなく、玉ねぎたらしめる「働き」のようなものだと説明する。
デカルトは近代科学の祖と言われるが、原点を「実体」視することで、まさに「主観‐客観」を定位させ、世界をモノとして取り扱う「科学」の礎を築いたのである。
一方のフッサールは「主観‐客観」の図式を超えて、この世界を形成する動的な根拠のようなものを示すのである。
これはまさに相対性理論以前の「近代物理学」と、量子論に代表される「現代物理学」との対話に類似する。
本書では単に「現象学とは何ぞや」を問う前に、哲学や科学がそれまで何を求め、どのような世界観を構築してきたかをおさらいするところから始めている。
したがって今現在における思想や科学のパラダイムを俯瞰する上でも、この「現象学」への理解は不可欠であろうし、さらにその壮大な哲学史観をとりあえずおさらいするには、本書は役に立つかもしれない。
もちろん本書を読んだところで、専門的な知識や考え方を身につけるには至らないであろう。あくまで「入門」ではあるが、そもそも「現代」が何を問題としているかを、基礎から考え直すためにも、一度は通過しておいて損はないであろう。