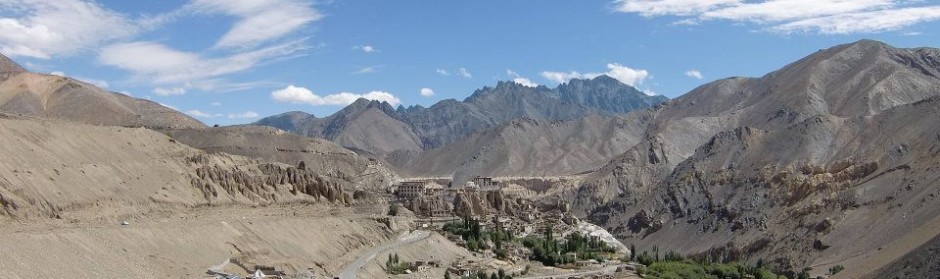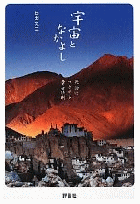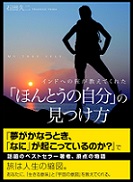- いわゆる「成功オタク」の中で著名な経営コンサルタントである神田昌典氏の新著。経営コンサルタントの本と言っても、よくある成功本の類ではなく、「近藤藤太」という実在した人物に関する評伝である。
その神田氏の一年ぶりの新著で取り上げられる、「近藤藤太」とはどんな人物なのか。本書の記述にしたがって箇条書きすると以下の通りである。
・富豪の家系に生まれるが、10歳の時に父が事業で失敗し、父逃避により、どん底の生活を送る
・ヤクザ稼業に身を落とした後、更正し慶応義塾大学入学
・学資稼ぎのために始めた音楽バンドが大ヒットし、ブロマイドが飛ぶように売れる
・太平洋戦争開始後、志願して陸軍に入隊
・金日成の捕殺の任務に就く
・戦後はGHQ、マッカーサー元帥の元で働く
・朝鮮戦争勃発を機に商社を創業し、大成功する
・その後、ポンドショックで破産し、巨額の借金を抱える
・岸信介元首相の下で働くとともに、「NHK英語講座」のキャスターを務めるなどしながら借金を完済
・72歳でオーストラリアに移住し、3人目の奥さんとともに悠々自適の生活
・88歳で癌により死去
神田氏の視点は、近藤藤太という「20世紀の巨人」を単に紹介したいだけはない。「日本経済は70年周期で周っている」という仮説のもと、70年前の大正・昭和の時代をワガモノに生きた、近藤藤太という巨人の生涯を反すうすることで、現代を正しく見通そうという意図がある。現代という時代は70年前と同じく、一歩先をも通せないほど、混沌と激動の時代にある。そんな中、我々はどのように生きていけばよいか、近藤藤太(トウタ)の人生からそのヒントが得られるかもしれない。
本書の前半は、トウタが富と貧困の生活を経て、太平洋戦争に至り、終戦後、多くの兵士を率いて、北朝鮮から無事に南朝鮮(韓国)まで逃げ延びた半生を描いている。とりわけ、北朝鮮から脱出する場面の描写がスゴイ。のどの渇きを小便を飲んで癒し、平壌の暴動の矢面に立ち。とにかく、紙一重のところで生き延びる。つまり、とことんツイてるのである。
本書の後半は、戦後のトウタのサクセスストーリーが展開される。まず、軍部情報部に勤めるのだが、英語のできるトウタは、司令官とともに米軍の幹部を訪問する。するとそこにはカルフォルニア大学の学友がおり、一気に信頼を勝ち得、その後はGHQへの推薦状をもらい、そこでも影響力を発揮する。その後、事故を機に本国(日本)で「商売」を始めるのだが、これがまた大当たり。そして人脈が人脈を呼び、瞬く間にビジネスのスターダムにのしあがっていくのである。こんな一文がある。
「人間は考え方で人生が決まる。でも残念なことに、多くの人は、自分なんえできない、自分なんてそれに値しないと決めてしまうの。自分で自分の能力に制限をかけちゃうのよ。」
トウタの成功には「自分に制限をかけなかった」ことが大きい。そしてまた、こんな文章がある。
「人生が新しいステージに行く時には、いくつかの進級テストがある。そのテストのことを多くの人は障害という。障害は避けようと思えば避けられる。だが、避けてしまった場合、進級テストにはパスしないのだから、結局、同じステージに留まることになる。やっかいなのは、テストはたいていの場合、抜き打ちでやってくるということだ。」
「障害」とは「進級テスト」なのである。人生の場合、なるべく苦労はしたくない、苦労しない人生に越したことはない、という人がいるだろうが、半ば納得しながらも半ば釈然としないところもある。しかし、「苦労=障害」と考え、背を向けるのではなく、「苦労=障害=進級テスト」と考えることで、前向きに立ち向かっていくことができる。トウタももちろん、成功の道のりにおいては、様々な進級テストにパスしてきたのである。
トウタの人生に停滞はない。事業に成功したかと思うと、為替のショックにより一気に破産。これなど、現代の大企業が一気に崩壊していく事実によく整合している。でもトウタは決して腐ることなく、百科事典の営業というゼロからのスタートを選択し、もちろん大成功。借金取に追われる傍ら、決して身隠れすることなく反対にテレビでの英語講座のキャスターを務めるなど、とことん前向きに人生を演出していく。
何があってもおかしくない現代だが、そんな時代だからこそトウタの生き方は大いなるヒントとなる。本書は一人の人物評伝でありながら、現代に通用する「成功法則」がいたるところに散りばめられてある。
自分を成長させる、より大きなツキを呼び寄せるには、自分より大きな存在と一緒にいる、大きなツキを持っている人と一緒にいることが重要だが、本書にはついぞ現れない「スゴイ」人物が描かれており、読むだけで「大きな存在」「大きなツキ」を得ることができるであろう。