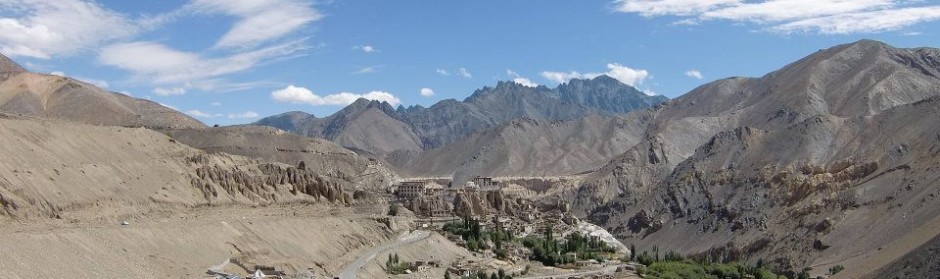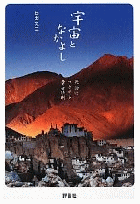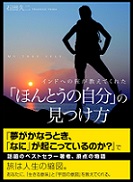「少年の名はサンチャゴといった」
で始まる冒険小説。
これは羊飼いの少年サンチャゴがスペインからエジプトのピラミッドまで宝物を求めて旅する冒険小説。ページ数にして200頁に満たない短い物語だが、この中には人生ワクワクして生きるエッセンスが豊富に盛り込まれている。
「『おまえが誰であろうと、何をしていようと、おまえが何かを本当にやりたいと思うときは、その望みは宇宙の魂から生まれたものなのだ。それが地球におけるおまえの使命なのだよ。』」(文庫版p28)
人は果たして本当にやりたいことをやっているだろうか。宇宙の使命を果たしているのだろうか。
「『おまえ何かを望むときには、宇宙全体が協力して、それを実現するために助けてくれるのだよ』」(文庫版p29)
この物語の最大のエッセンスとも言えるフレーズ。人が本当に何かを望むことに『熱中』しているときは、宇宙全体がそれに協力する。バシャールが「ワクワクするものこそ宇宙から与えられたその人の使命」と言っていることにシンクロする。斎藤一人氏が「『楽しい」を基準にして仕事をすれば全てがうまくいく」と言っていることにシンクロする。しかし、多くの人は自分のやりたいことを犠牲にして人生を終えていくもの。
「『パン屋は自分の家が持てる。しかし、羊飼いは外で寝なくてはならないからね。親たちは娘を羊飼いに嫁にやるより、パン屋にやりたがるものさ』」(文庫版p30)
サラリーマンは家族を養える。しかし、フリーランスは明日の飯を心配しなくてはならないからね。親たちは娘をフリーランスにやるより、サラリーマンにやりたがるものさ、、、と聞こえる。
かくして少年はピラミッドに向かって旅のだが、途中、泥棒に所持金を盗まれたり、戦争に巻き込まれたり、暴漢に出会ったりする。しかし、本当に何かを欲している時は全宇宙が協力する。少年は泥棒に所持金を全て盗まれたとき、こう考える。
「自分のことをどろぼうに会ったあわれな犠牲者と考えるか、宝物を探し求める冒険家と考えるか、そのどちらかを選ばなければならないことに気がついた。『僕は宝物を探している冒険家なんだ』」(文庫版p51)
自分のことをリストラされたあわれな失業者と考えるか、自分の好きなことができるフリーランスと考えるか、、、と聞こえる(笑)。人は人生の中で楽しいこと、悲しいこと、居た堪れないこと、いろんな経験をするもの。しかし、「自分は何がしたいのか」を真剣に考え、それに『熱中』することで、自分が宇宙から与えられた使命を果たし、全宇宙が協力してくれる。
仮に目の前で悲しい現実が立ちはだかっていようと、宇宙は全ての人を必然・ベストの方向の向かわせるのだ。物語の言葉を借りると、「マクトゥーブ(全ては書かれている)」なのである。ただし、人は運命を信じなければならない、前兆にしたがって生きなければならない、前向き出なければならない、それだけで宇宙は協力してくれる。
かくして少年はピラミッドまで旅を続ける。そこで見たものは。。。
自分の人生に疑問を持ったとき、そして、よりワクワクした人生を送りたいと猛烈に願ったとき、、、この物語は人に何かを示唆するでしょう。人生の必読書。
- アルケミスト―夢を旅した少年 (角川文庫―角川文庫ソフィア)/パウロ コエーリョ

- ¥580
- Amazon.co.jp