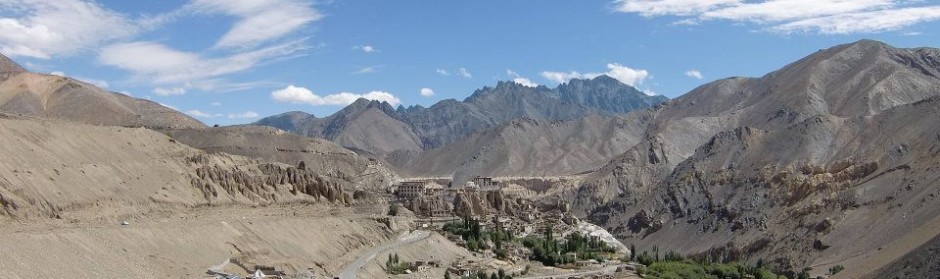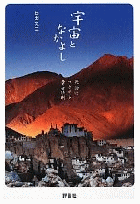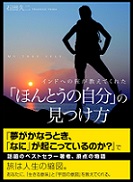- コールドリーディングのテクニックをセールスに応用したノウハウ本。森下氏の著となっているが、元ネタの大半は石井裕之氏のものであることがわかる。それを接客・セールスのプロである森下氏が自身の専門的立場から編集しなおしたという内容。
読んだだけですぐに使えるようになるかはわからないが、上手にセールスをするには是非とも知っておくべきテクニックが満載。その中心は偽占い師のテクニックとして日本に紹介されたコールドリーディング、つまり何の準備もせず、初対面で相手のことを深く理解していると「思わせる」技法のこと。
しかし本書の真意としては、もちろん相手を騙すことにあるのではなく、「一瞬で信頼関係を作る方法」を軸としている。セールスの基本はお客さんとの「信頼関係」を築くことにあるのだから。
それにしても確かに面白い。偽占い師が使うとされている「ストックスピール」をお客さんとの雑談(オフビート)の際に使うなど、タイミングを間違えれば逆効果だが、うまくはまれば確かにお客さんからの信頼度は増すだろう。本書の例ではないが、アパレルなどで接客する際、少し世間話ができれば、さりげなく「お客様も今変わろうとしている時期みたいですね」などと言うと、相手はイチコロかもしれない。服を買いに来る人は何かしら「変わる」という願望があるのだが、潜在意識下にあるその願望を、言葉によって目覚めさせることで、相手(客)は店員に深い信頼関係を得るであろう。するとお客はその店員から買わざるを得なくなる。そのような「ストックスピール」の例が本書ではいくつか紹介されている。
その他、「イエスセット法」「ノーセット法」「ダブルバインド」「サトルネガティブ」「サトルクエスチョン」「結合法」「Me/Weタイプ」などのテクニックが紹介される。これらのテクニックは石井氏の著書でも既に紹介済みではあるが、本書はこれらをセールスに生かすことに重きを置いているので、各項目ごとに「セールスで使う○○」などと、具体的に例文を示しながら解説されているところが親切だ。実際、それらの例文を読んでいるだけでも、ある種の臨場感を得ることでセールスに対するブロックは少なからず解かれるかもしれない。
このように本書には非常に「使える」テクニックが満載で、手元に置いておく価値はあると思われるが、私個人的な感想として、読者にはどうしても注意を促したいことがある。確かにこれらのテクニックを知ることでセールスに対する恐怖心は幾分は薄れるかもしれない。だからと言って、いきなりこれらのテクニックを使うことは逆効果の場合があることを知っていてほしい。
例えば本書に紹介される以前からセールスプログラムでよく見られる「ダブルバインド」などは、相手との信頼関係や購買意欲のない段階で使うと、大きな火傷をする可能性もある。「ダブルバインド」の一例としては「一括になさいますか?それともローンになさいますか?」などと、どちらに転んでも「買う」ことが前提とされているようなトークが代表だが、店に入ったばっかりの単に見ているだけのお客にこれをすると、お客は瞬時に店から出ていくであろう。さすがにこれは極端な例であるが、本書で紹介されているテクニックを使って、仮に失敗したところで、そのテクニックのせいにすべきではないだろう。
これらのテクニックは、テクニックとして初めて開発されたものではなく、多くは(否、すべては)、既に優れたセールスマンが無意識的に用いていた技術なのである。もう一度言うが、セールス経験のない新入社員がいきなりこれらのテクニックを読んだだけで用いては失敗する可能性が高い。その際、くれぐれもテクニックのせいにしないこと。あくまで使う側のセンスと経験によるものだという理解を促したい。
あえて本書の活用法を一つ付け加えるとすれば、実際に使いたいのであれば、決して「読むだけ」にはしないことだ。非常に丁寧に記されている数々の「例文集」を是非音読してもらいたい。できるだけ何度も。それも棒読みでなく臨場感を感じながら。そうすることで、幾分はテクニックが「使える」ということを実感できるだろう。本書は石井氏によるこれまでのコールドリーディング本よりもさらに「実用書」として繰返し読み、練習することで、ようやく本の効果が現れるものだと考える。