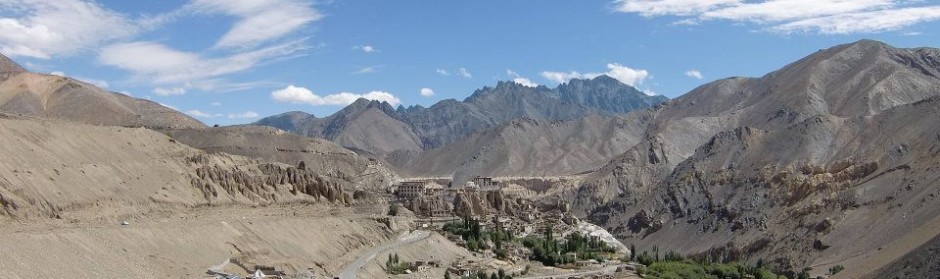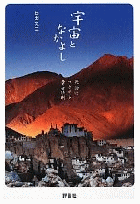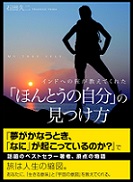本書については殊のほか、思い入れが強い。
私の人生を変えた、と言っても過言ではない、伝説の人物に関する本であるからだ。
私はまだその「伝説の人物」に直接会ったことはない。その人物が開く社内研修のビデオで姿を見るだけである。しかもその録画は劣悪。研修の内容ではなく、映りが劣悪ということ。それでもその内容、その中の人物のパワーには驚かされる。
その「伝説の人物」とは、謎のスーパー営業マン、加賀田晃氏のことである。本書は加賀田氏の社内研修の模様を正確に描写したものである。
加賀田晃氏のことを簡単に紹介すると、中学校を中退後、様々な職歴を経て23歳でセールスの世界に入る。
現在は主として企業向けに営業研修業を行っているが、それまでの間、17社の会社を渡り歩き、そのすべてにおいてトップの成績であった。
一番最初の会社は防犯ベルの飛び込み営業。初日にして100%の成約。ある教材販売のセールスでは99%以上の成約率。
大阪で北海道の土地(原野)を売る飛び込み営業においては、会ったその日に現金を貰うまでの過酷な営業を、なんと80%の成約率で成し遂げていたとか。
また、住宅販売においては、20人以上の営業マンが2年間で3棟しか売れなかったものを、残りの27棟を「たった一人で、たった一ヶ月で」売り切ってしまった。
しかもそれは冷やかしも含めた、たった29人のお客を相手にしてである。
通常、3%の成約率があればそこそこの営業マン。
10%もあればスーパー営業マンと言われるのだが、加賀田氏の場合は、とにかくその数字が桁外れである。そして今もなお、現役の営業マンであると言う。
加賀田氏をして「営業」とは何かと聞くと、それは「誘導の芸術」であると言う。
それは決して騙したり脅したりして強引に売り付けるものでもなく、または低姿勢に懇願して買って頂くやり方でもなく、とにかく、営業のプロセスで相手を「買いたくてたまらない」という状況にまで誘導することであると言う。
言い換えると「無」と「否」を「有」に変える芸術であると言う。
さらに加賀田氏のすごいところが、本人だけでなく、加賀田氏の所属するグループ、部下までもが例外なく売上が倍増し、また、加賀田氏の研修を受けた営業マンやその会社までも目を見張るような成果を獲得するという点である。
営業とは決して「天賦の才」ではなく、その「セオリー」さえ身につければ、概ね一ヶ月、遅くとも二ヶ月もあれば間違いなくプロになれるものだと言う。
本書はその営業研修のライブ収録である。
本書は大きく「哲学編」「セオリー編」「話し方編」「抵抗解決編」「礼儀編」「極意編」に章が分けられている。
「哲学編」では「セールスとは何ぞや?」を語り、「セオリー編」では実際の現場におけるアプローチからクロージングまでの方法論について説明する。
「話し方編」ではセールスの基本となる、文字通り「話し方」の実際、「抵抗解決編」ではセールス現場で必然的に生じる「抵抗」を切り返すテクニックについて。
「礼儀編」では扉の開け閉めから、挨拶、座り方に至るまでの「べくべからず」を説く。
そして最後の「極意編」ではまさしくセールスの極意。その極意とは3つ。
それは「愛対意識」と「当然意識」と「不諦意識」である。
その3つの極意について、加賀田氏の実際の体験を交えながら力説する。
まず「愛対意識」とは相手をとことん「好き」になって接すること。
「当然意識」とは文字通り、当然のように振る舞うこと、相手が当然買うものだと思って振る舞うことである。
最後の「不諦意識」とは決して諦めないこと。この話がすごい。まさしく「営業の鬼」を感じさせるエピソードが紹介されている。
本書はよくありがちな精神論でもなく、使えないテクニックの羅列集でもない。
まさしくプロのセールスマンになるための具体的な「実用書」である。
そして私も「実用」している。世の中には数多くのプロと呼ばれるセールスマンがおり、その何人かはご丁寧にもそのノウハウを著書などで紹介してくれている。中にはそれで有名になっている人もいる。
しかし、加賀田氏はそのいずれと比べても間違いなく段違いの凄さである。このような人物が存在するなどにわかに信じられない。
余談であるが、私はまだ加賀田氏には直接会ったことがないが(注:この後に実際に研修を受けることができた)、氏の研修を受けたことがある人と話たことがある。
いわく、氏の研修を受けた途端に、その会社の売り上げは瞬く間に上昇し、その研修にはまり込んでしまった社員は、すごい勢いで実績を出し、出世街道を走るようになったのだと言う。
伝説は決して誇張ではなさそうだ。本書はまさしく「営業の聖書」である。
- 必ず売るための「究極の説得」の秘密―こんなに凄い売り方があったのか 加賀田式セールスの極意を大…/大友 義隆
¥1,470 - Amazon.co.jp