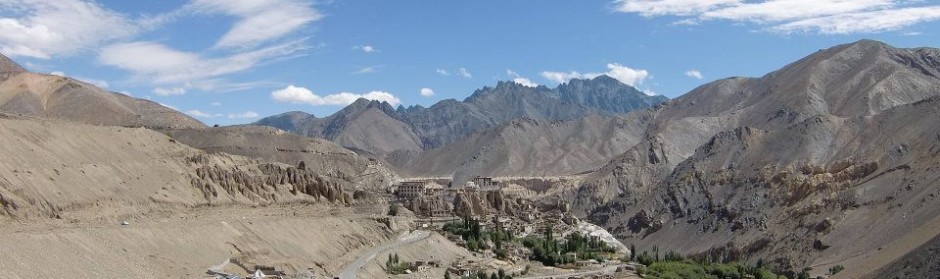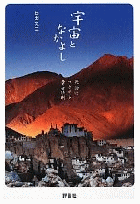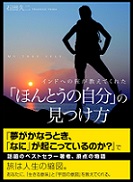「すみません・・・5枚だけなんですけど、先にコピーとらせてもらえませんか?」
「すみません・・・5枚だけなんですけど、急いでいるので先にコピーとらせてもらえませんか?」
「すみません・・・5枚だけなんですけど、コピーをとらねばならないので先にコピーとらせてもらえませんか?」
図書館のコピー機の前にいる人にこのように頼んでみた。どれくらいの人が、この頼みに応じるだろうか。
一番目では60%の人が承諾したのに対し、二番目ではなんと94%もの人が頼みに応じたのである。
理由はなにか。一番目は単に頼んでいるだけであるのに対し、二番目は「急いでいる」という合理的な理由を付け加えたからだろうか。
実際にそうでないことが、三番目の承諾率を知ることで理解させられる。
三番目は実に93%もの人が頼みに応じているのである。
つまり二番目と三番目はほとんど同じ承諾率なのであるが、見ての通り、三番目は何ら合理性のない理由づけである。
ここで重要なのは「ので」である。
人は「ので」という言葉を聞いてしまうことで、自動的に同じような行動パターンを取ってしまうのである。この例では依頼に対する承諾である。
本書ではこのような、いわば条件反射的な固定的行動のことを「カチッ・サー」という言葉で表現する。
つまりテープレコーダーを「カチッ」とオンにすると、すぐに「サー」とテープが動きだすことのメタファーである。
本書はこのような合理・非合理関わらず、ある種の固定的な行動パターンの本質を解き明かす。
なぜ人は欲しくもない高額な布団を買ってしまうのか?
一通のダイレクトメールだけで商品を注文してしまうのか?
見も知らぬ人に対して高額な寄付に応じてしまうのか?
まさしく「カチッ」とスイッチが押された瞬間、「サー」と自動的に一定の反応をしてしまうのである。
本書ではその「カチッ・サー」の原理を6つの法則によって説明する。それは、
1.返報性
2.コミットメントと一貫性
3.社会的証明
4.好意
5.権威
6.希少性
である。簡単に説明したい。
1.返報性
いわゆる「お返しの法則」である。デパートの試食コーナーはまさしくこの原理で成立している。つまり食べてみて美味しいから買うのではなく、試食させてもらったお返しとして人はそれを購入するのである。
相手に譲歩を促す場合もこの法則が活用される。販売においてまず最初は高額な提案をし、そこから値引きという譲歩をすることで、相手はその譲歩に対するお返しとして、その商品を購入してしまう。「拒否したら譲歩」、、これによって相手はジワジワと意図せぬ承諾へと追い込まれる。
この法則に対する防御としては、最初の提案を常に拒否することではなく、受け取った上で、トリックだと再定義することである。
2.コミットメントと一貫性
人は自分が一貫した人間であると思いたがる。高額な自己啓発セミナーの説明会に参加したとしよう。実は参加したという時点で、自分は自己啓発に興味があることを示している。主催者からすると、参加者はその時点で見込み客ではなく「顧客」なのである。
ではそのセミナーが想定以上の高額の場合はどのようにすればいいのか。まずは低額な商品を買わせることである。低額であれ、商品を買うというコミットメントを引き出すことによって、いずれは高額商品をも購入してしまう。
クーリングオフの防止においてもコミットメントの効果は大きい。それは自分で契約書を書かせるというコミットメントを引き出すことである。自分で契約書を書いた以上、その商品は価値あるものだと一貫性を保ちたくなる。
人から巨額な寄付を受けることも容易である。相手に自分自身が慈善家であるというコミットメントを引き出せばいいからである。それにより慈善事業に対する寄付を拒むことはできなくなる。
一貫性に基づく承諾誘導への防御法は、身体的な違和感に従い、それが馬鹿げた一貫性誘導であること要請者に伝えることだ。もう一つは最初のコミットメントが時間が遡っても同じコミットメントをもたらすものか自分自身に問いかけすることである。
3.社会的証明
多くの人間はテレビの「録音笑い」に嫌悪感を示す。それは聴衆だけでなく、テレビで演じている役者においてもである。役者はしばしば「録音笑い」を止めるようディレクターに要請するが、これほど嫌悪されているにも関わらず、「録音笑い」がなくなることはない。なぜなら番組制作者は「録音笑い」が効果的であることを学術的に知っているからである。
ここには社会的証明の法則が働く。人は自らの判断が不確かな場合、その判断を他人、社会に求める。理性的には面白いと思わなくとも、社会がそれを面白いと受け止めていると、自分自身も面白いと思うことが正しいように思うからである。
「さくら」の原理もこれである。ある店頭で多くの人が並んでいたら、自らもそこに並ぶことが正しいように思え、結果として、欲しくもない商品を購入してしまう。
社会的証明への防御法は、それ(例えば「録音笑い」)が意図的に作られた操作で、明らかに偽りの証拠であることに敏感になることである。類似した他者の行動だけを決定の基礎にしてはならない。
4.好意
世界ナンバーワンのカーセールスマンとしてギネスブックにも認定されたジョー・ジラードは販売の秘訣をこう語る。適正な価格を示し、この人から買いたいと思われる人間になること、この二つで誰でも車を買うようになる、と。ここで重要なのは、人は好意を寄せている人からものを買うということである。
そこで好意を高める方法がセールス等において重要となる。ジラードは毎月数千枚のはがきを顧客に書いたが、そこには「あなたが好き」と必ず書くようにしていた。人は自分のことを好きと言ってくれる人を好きになるものだ。たとえそれが偽りであっても。他にも身体的魅力、類似性、親密性など好意を高める方法はいくつもある。
好意によってもたらされる承諾誘導への防御法は、要請者に対する過度な好意に敏感になることである。つまり好きな相手に対して一歩引くことが肝要なのである。
5.権威
特定の症状に効果的だとうたわれるサプリメントがあったとしよう。値段も安くはない。知人から勧められるに従ってそれを購入する人はどの程度いるだろうか。有名なタレントのCMだけで購入する人はどの程度いるだろうか。しかしこれが「専門家」の勧めとなると事態は大いに変わってくる。購買意欲は劇的に上がるであろう。
つまり人は権威に弱い。さらにその権威に実体がない場合でも、その権威のシンボルとなる肩書き、服装、装飾品を示されるだけで、承諾を受け入れてしまう。
権威に基づく承諾誘導への防御手段は、その権威(専門家)は本当に専門家か、どの程度誠実だと考えられるかについて、問いかけることである。
6.希少性
ある宗教施設は信者しか中に入ることが許されない。たとえ改宗の可能性がある人であっても。しかし、それにはひとつだけ例外がある。その施設が新築された直後の数日間は、誰でも見ることができるのである。このとき、その宗教にまったく興味のない人間であっても、なぜか見に行きたくなるものである。なぜか。この機会を逃したら二度と見ることができなくなるかもしれないからである。
これは希少性の法則と言われ、手に入りにくいものほど、それがより貴重に思えてくるのである。有名ブランドが手がけた数千円のエコバッグを求めて多くの人が列を作ったことは記憶に新しい。なぜならそのバッグはまさしく限定商品だからである。
実際には価値がなくとも、希少であるというだけで、その商品は実に魅力あるものに思えるのである。この希少性に基づく承諾誘導を防ぐには、瞬間的な購買意欲と興奮を抑え、なぜそれが欲しいのかという観点をとることである。
以上のように、本書は人の購買意欲や承諾要求を高めるための禁断の術、影響力の武器が豊富な事例とデータによって紹介される。
対面セールス、インターネットマーケティング、などいずれのケースにおいても、即効性のあるノウハウが惜しげもなく提示されるが、ややすると悪徳商法にも利用されるであろう。
私は今このような素晴らしい情報を提供している。
このブログを読む人は、少なからずビジネススキルの向上に関心を寄せる。
そして多くの人がこのブログを見て、実際に本を買っているし、本書に寄せるレビューも信じられないくらいに評価が高い。
もちろん私はこのブログを読む人に、他ならぬ行為を寄せてしまう。
さらには私が紹介する本に外れはないと評判である。
最後に「影響力の武器」は知る人ぞ知るノウハウであり、知るだけでトップの数パーセントに入ることができる。
以上の文言は「影響力の武器」をあざとく再現したものである。
もし「影響力の武器」を買いたくなったら、まさしくその罠にかかったことになり、買いたいと思わなければ、防御できたことになるかもしれない。
しかしここで防御することは、本当にあなたの人生によき実りをもたらすのであろうか。
3,000円で人生が変わる人もいれば、それを惜しむことで、変化のない人生を余儀なくされることもある。
しかし、本当に買ってしまえば、あなたは簡単に罠にはまってしまったことでもある。
本書には書かれていないが、これが有名なダブルバインドである。
- 影響力の武器―なぜ、人は動かされるのか/ロバート・B・チャルディーニ

- ¥3,465
- Amazon.co.jp
- 影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか/ロバート・B・チャルディーニ

- ¥2,940
- Amazon.co.jp
- 影響力の武器 実践編―「イエス!」を引き出す50の秘訣/N.J.ゴールドスタイン

- ¥2,100
- Amazon.co.jp