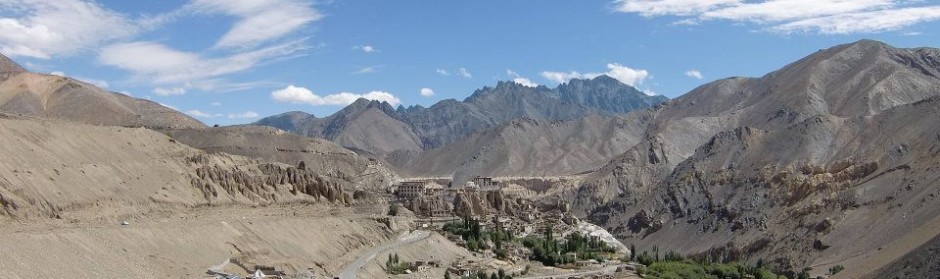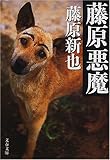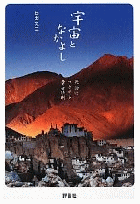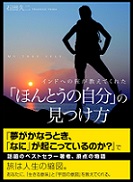2007年に入ります。
実はこの年はある意味、記念すべきターニングポイントとなる年だったと言えるでしょう。
そして収入的には、複数の収入源を確保しながらも、あるモノだけが突出して、しかもそれに関して2007年はピークを迎えました。
この状況がずっと続けば、何の心配もなく、好きなことだけやっていられます。
そしてこの状態は、奇しくも加賀田DVDを初めて見たときの、
「もしもこのDVDをマスターすれば、オレはもうお金に困ることはない!」
という確信が、そのまま現実化したものだったのです。
しかし、現実とは裏腹に、なぜか私の心は満たされない。
むしろ収入が増えれば増えるほど、何かしらの心配が付きまとうのです。
それもそのはず、その時の収入は、経緯だけから見ると出会い頭の偶然であり、自分の力で勝ち取ったもではない、、、という不安感だけが付きまとっていたら。
結局、オレは何をやりたいのか?
そんな時、日ごろから親しくして頂いている知人が、投資関係のセミナーを開催すると聞きました。
その時さらに、「Qさんも、何かしゃべってよ」と言われ、2秒で即答しました。一月のこと。
今思うと、その時、何を話したのか覚えてないし、ちゃんと喋れたかどうかもわかりません。
時間にして30分程度だったと思います。
おそらく潜在意識がどうとか、、、と言う話をしたのだと思います。
しかし、そこで得たものは、その時の私にとってあまりにも大きなものでした。
もちろんギャラを頂くようなものではなかったものの、20名以上の前で30分間お話をする。
それもセミナーという形式で。
これはもしかしたら何かできるなじゃないかと、ひらめいたのです。
そんな時、前の年の東京オフ会で知り合った、ある人のことを思い出します。
その名を「幸せまん」と言います。
その時のオフ会では、幸せまんがどのような人だったのか、あまり深く知ることはできませんでした。
ただ、そのオフ会で私に会いに来てくださった、ある女性の方が、その翌月辺りに幸せまんのセミナーに参加したそうなんです。
そして幸せまん本人から、「Qさんのおかげで、一人セミナーに来て頂けました、ありがとうございました」というお礼のメールを頂いていたのです。
ふとそのことを思い出しました。
セミナー、セミナー、セミナー、、、、、、
そうだ!セミナーだ!
実はその時、幸せまんがどのようなセミナーをされていたのか知りませんでした。
なにやら投資関係の仕事をしているとかいないとか聞いていたので、てっきりそっち系かと。
実際は全然違っていたのですが。
とりあえず、オレもセミナーやろう!
しかしどうやっていいのかわからない。
そうだ!幸せまんとジョイントさせてもらったらいいのでは。
受けて頂けるかどうかわからないが、一応、私のブログの読者さんが彼のセミナーに参加したと言うので、嫌な顔はさらないだろう。。。
てなことで、その一月の30分間のゲストセミナーの直後に、幸せまんにメールをしてみたのです。
東京でジョイントセミナーをやって頂けないかと・・・・
すると、幸せまんは快諾!
ぜひやりましょう!
ってことで、日程は半年後に。
なぜそんなに時間が空いたのかと言うと、幸せまんに4人目の子どもが生まれるとかなんとか。
一月に一応、約束だけして、、、、しかしそのまま凍結状態となりました。
・・・かのように見えたのですが、幸せまんの子どもが生まれて一段落した4月頃、幸せまんの方から連絡が。
「セミナー、どうしますか?」
気になっていた。
「は、はい、やりましょう!」
「で、日にちは?」
「6月の土曜日辺りどうですか?」
「じゃあ、その辺の日程で検討しときますね」
と言うことで、結局、「6月9日」に決まったのです。
事務的な用意は、すべて幸せまんがやって頂けました。
会場の予約、申込フォームの作成、その他。
とにかく、初のセミナー。
5人も来て頂ければ万々歳、、、と思いきや、アナウンスした直後に連絡が。
「Qさん、もう10名超えてますよ!」
「マジッすか~!」
そんなこんなで、ふたを開けてみたら、25名もの方に来て頂けたのです。
オフ会などで私と会ったことのある方もいらっしゃいましたが、ほとんどが初対面です。
約4時間のセミナーで、前半が幸せまん、後半が私です。
ただ、不思議なことに、まったく緊張はしていませんでした。
それよりも、早くオレの番にならないかと、そわそわ、わくわく。
そしてようやく私の出番がやってきました。
持ち時間は約90分です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あっという間に、時間が来てしまいました。
自分的にはウマくいった感じ。
会場の反応も悪くない。自己採点は80点以上。
しかし、会場は騒然。本当の騒然。
幸せまんからは、、、、「い、いや~、すばらしかった、ほんとうに・・・」と、まんざらお世辞でもない称賛を。
そして幸せまんの友人の不動さんと言う方からも、、、「え?今日が初めて?10年のベテランかと思った!」、と。
他には「中村文昭っぽい感じだね」とか「Qさん、すごいね」、、、など、私が思っていた以上の反応。
こ、これだ!
オレがやりたかったのは!
これが私の初の有料セミナーであり、伝説の69セミナー。
すべてがここから始まった。
ちなみに余談ですが、この会場にいた約25名の中から、その2年後、カップルが誕生しました。
おそらくその日、その二人は言葉を交わすこともなかったろうけど、やっぱりここから始まっていた。
今はもう、素晴らしいご夫婦となりました(結婚式には行けなかったけど・・・)