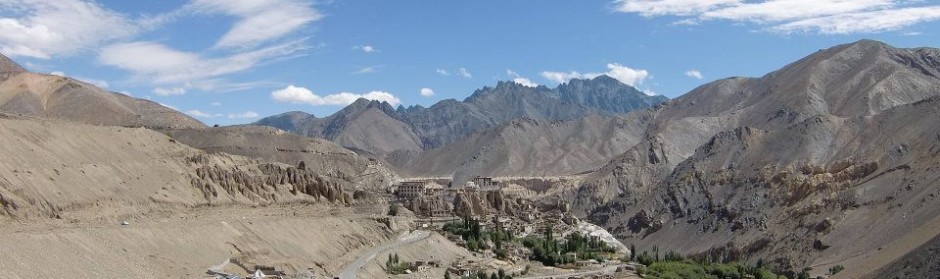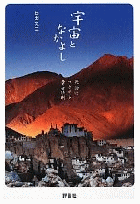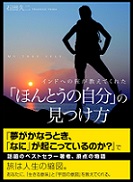アメリカのマーケティング界で最も影響力がある人物が本書の著者であるダン・ケネディ氏である。
本書の邦題は「大金持ちをランチに誘え!」であるが、正直、これでは内容があまり伝わらない。
さりとて、原題を直訳した「究極の成功の秘訣」では、陳腐すぎて書店では並びにくいのだろうか。
しかし、本題はまさしく「究極の成功の秘訣」であり、「成功法則」と呼ばれるものは数多あるが、もしもたったひとつの究極の秘訣があるとすれば何なのか、が主題である。
その答えは最後まで読んだときに明らかになるが、本書を読む途中からそのメッセージは響いてくる。
本書の「成功法則」に甘やかな蜜を求めているのであれば、ひどく火傷するであろう。
「究極」と呼ばれるだけあって、生半可ではない。
しかしそれは確かに「究極のひとつ」であることは間違いない。その「ひとつ」はこのように説明される。
「そして私は、その「ひとつ」を見つけた。人並み外れた成功者たちのすべてが、ほかのどの成功の秘訣よりも、普遍的に共有し、頼りにしているたったひとつの「成功の極意」である。」
その「極意」は一言で言い表すことができる。
しかし著者の言うように、本当に「一言」で言ってしまえば、おそらく読者には伝わらないだろう。
本書を読み進めていく上で、その「謎」を解いて欲しい、というのが著者の意図するところである。
本書ではところどころに読者の胸をつんざくようなフレーズが登場する。例えば
・他人に頼って幸せになろうと思っている限り、いつまでたっても幸せにはなれませんよ
・いつまでチャンスを棒に振り続けるの?
・あなたは何を待っているのですか?
・やりもしないでどうしてわかるの?
・あなたのことなど誰も気にしてない
・大金持ちをランチに誘え!(本書の邦題であるが、実際には全体の中の一節である)
・売り込まないと恐ろしいことになる
・ひたすらシュートを打ち続けよう!
などなど。
一見してかなりストイックな印象があるが、実はその通りである。
だからこそ生半可な気持ちで手にすると火傷する。
しかしそれを受け入れることなしには「成功」の二文字はおぼつかないであろう。本書は確かに「ひとつの極意」と呼ばれる、単純な法則が全体を貫いているが、各章は独立した内容になっているため、どこから読んでもさほど差し支えはないだろう。
私自身が特に響いたのが「直観力を研ぎ澄ます話」と「売り込みの達人になる話」である。
前者はしばしばやってくる「ひらめき」に敏感になり、その通りに行動すると、よい結果を得ることがある、と言う話である。
後者は「売り込み」に否定的な感情を持つことなく、イエスキリストがそうであるように、売り込みの達人になれ、と言う話である。
その他にも本書には胸を打つ話が多い。ハッと目覚める話が多い。
それでは成功のための「究極のひとつ」とはいったい何なのか。気になれば、ぜひ、本書をお読み頂きたい。
- 大金持ちをランチに誘え! 世界的グルが教える「大量行動の原則」/ダン・ケネディ

- ¥1,470
- Amazon.co.jp