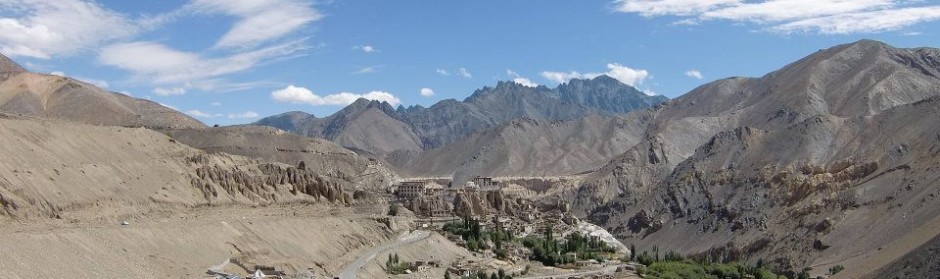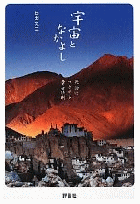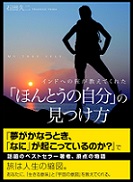古典的名著(?)として知られる「かもめのジョナサン」だが、人から勧められたので、初めて手に取って読んでみた。
テキスト自体は一時間もあれば読める。主人公はジョナサンという名の「だいぶ変わったかもめ」である。
鳥は食べるために飛ぶ。しかしジョナサンは「飛ぶ」ために飛ぶという、群衆とは違った目的を持つようになる。
人は何のために生きるのだろうか、という問いかけにも感じる。
前半、ジョナサンは群れから追放されながらも、思考錯誤を繰り返しながら、飛ぶことを極める。自己実現する。
しかし問題は後半部である。飛ぶことを極めた先には、瞬間移動の術、蘇生の術などを身に付け、それを弟子に伝授する。
人は無限の可能性を持っているというメッセージ性を感じ、ジョナサンの生き方、考え方に大いに共感する人も多いだろう。
しかし、一方において、どこか相容れない「違和感」を感じるものもあるだろう。
その違和感については訳者である五木寛之氏が解説で述べている。
五木氏はこの当時「青年は荒野をめざす」を著し、自由に旅立つ若者の精神的支柱となっていた。
「かもめのジョナサン」も同様に、組織や群れから自由になり、無限の可能性を追求する若者の鼻息荒さを表現している。
にも関わらず、五木氏は「かもめのジョナサン」に「違和感」を感じると述べているのは、非常に興味深い。
多くの読者が指摘するように、本書は一種の神秘主義的新興宗教のバックボーンとなっているかもしれない。
そしてそれは日本における「現代スピリチュアリズム」に受け継がれていると見るのは難しくない。
いわゆる「アセンション」に向けて、今、すべきことは何なのか。
物質文明から脱却し、真なる人間性、精神性を追求せよ。社会的な反発に直面しても、ジョナサンのごとく、例え「悪魔」と言われようとも、求める先には光を見るのだ、と。
五木氏の違和感もここにある。人は「さながら」に生きてもいいのだ。
食べるために生きようが、飛ぶために生きようが、価値は等価であり、大衆と違った生き方をすることだけが優れていると錯覚するべきではない。
「さながら」に生きることもまた勇気なのである。「選民思想」的な心地よいまどろみに毒されてはならない。
ジョナサンの生き方も一つの生き方。そうでない生き方にも素晴らしさや幸せがあることを今一度確認したくなる一冊だった。
私自身がジョナサン的な生き方に憧れをもつだけに。
- かもめのジョナサン (新潮文庫 ハ 9-1)/リチャード・バック

- ¥500
- Amazon.co.jp