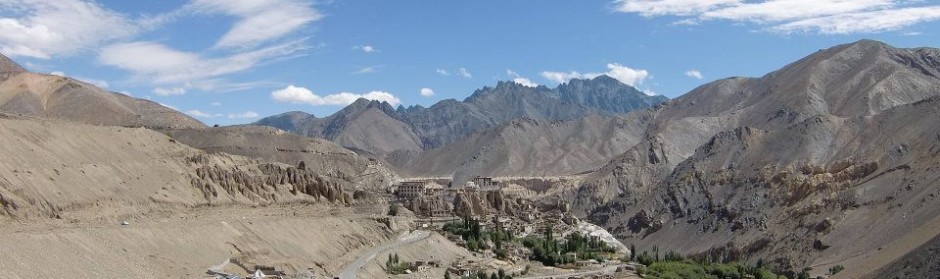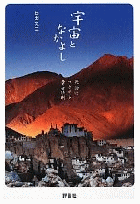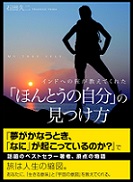私ごとで恐縮だが、「ドラえもん」のコミック(第一巻)を初めて読んだのが、小学一年生の時である。
それまでヒーローものの図鑑や昆虫の本など、絵や写真を見るだけの本し読んだことがなかったのが、生まれて初めてストーリーとなるものを読んだのが「ドラえもん」であった。
あの時の衝撃は今でも忘れない。もともとは兄のために父親が買ってきたものだった。兄はそれを何度も繰り返し読んでいたが、私はカブトムシの本にばかり関心が向いていた時期だった。
何かの拍子に手に取った「どらえもん」がすんなり読める、という感動もさることながら、そのストーリーにぐいぐいひきつけられ、それから「ドラえもん」のコミックを買ってもらうのは、私の役目になった。
桜井進氏による本書のプロローグにこのような一文がある。
「自慢でも何でもありませんが、私は、『ドラえもん』のストーリーやセリフを聞いたとたん、パッとその状況が浮かんできて、それが何巻に描かれていたものかをほぼ正確に答えることができます。」
正直、これは私のことでもある。私自身もまた、登場する秘密道具、セリフなどを聞いた瞬間、その時のストーリーをリアルに再現できる。たとえば「コーラも飲まず、クリームも飲まず」というのび太らしいキッチュに富んだセリフは「ラジコン大海戦」からである。
それはそうと、本書であるが、科学の専門家が「ドラえもん」に出てくる道具の実現可能性について、科学の目線から検証しようという、非常に興味深いテーマが貫かれる。
実は藤子F不二雄氏は大のSFファンであり、科学についての造詣も深い。それはF氏の短編集に顕著に現れるが、もちろん「ドラえもん」にもだ。少年時代にビックリしたのがワープの原理。宇宙戦艦ヤマトなどでは、それっぽいトンネルのような空間を走っていたと思うのだが、「ドラえもん」で説明されるのは、「空間を曲げる」という理論。まさしく「相対性理論」ではないか。
また、第二章では「量子論」の理論を「ドラえもん」の道具への応用と絡めながら説明しているが、これが実にわかりやすい。ややもすると、概念的に過ぎる「量子論」の内容を、「どこでもドア」などを引きあいに出しながら説明する。
そして後半では、環境問題や科学偏向への危惧を示すが、ここでも「ドラえもん」の話は非常に示唆に富む。さらには科学の話から発展し倫理観や人生観へも展開する(「さようならドラえもん」など)。
著者は「ドラえもん」に流れるこのような「人間観」こそが、道具に見られる「科学」への視点を生きたものにすると指摘する。まさにその通りであろう。まさに「ドラえもん」は科学を、そして人生を教えてくれる生き方のバイブルなのである。
本書には著者の「ドラえもん」に対する愛、そして科学や人間に対する信頼感があふれているように思う。いい本だな~と思った。
- 2112年9月3日、ドラえもんは本当に誕生する! (ソフトバンク新書 49)/桜井 進

- ¥735
- Amazon.co.jp