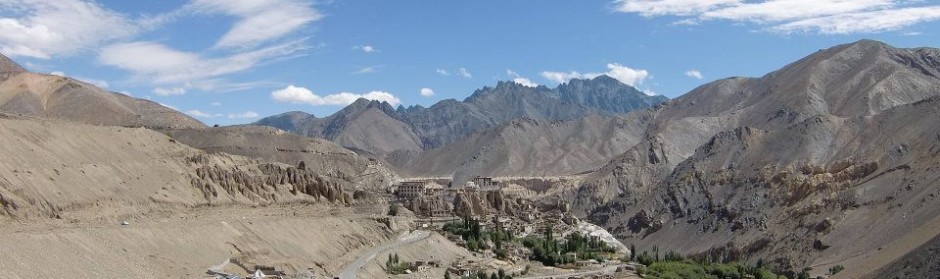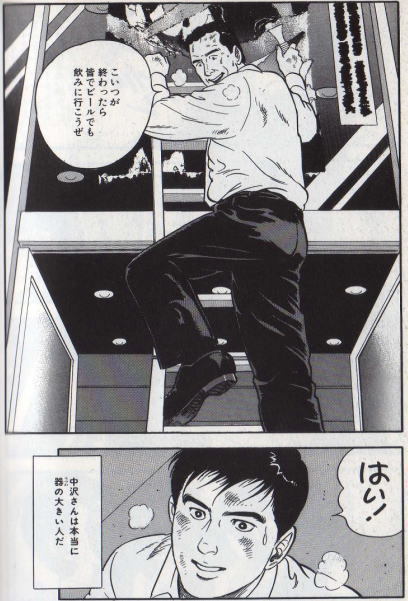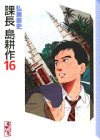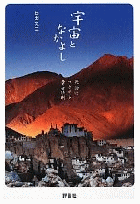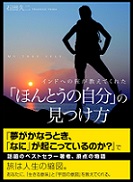個人的な話であるが、1999年8月に約20日間ほど、アイルランドを旅行した。
実は「傷心旅行」であり、傷ついた寂しい心を癒すのに、どこに行こうか最初は悩んだ。
どうせならまだ一度も行ったことのない国がいい。
東南アジアはインドネシアやベトナムが残っていたが、そんなエネルギッシュな国に行くと、余計に寂しくなるだろう。
そんな時、妙に心に響いたのが「アイルランド」である。
「アイルランド歴史紀行」はその時に持って行った一冊である。
なんとなく堅そうなイメージを受けたが、読み始めると、これが面白い。
著者の高橋氏の本業は経済学者(イギリス経済史)であるが、一般向けの著書としても、歴史、ミステリー、グルメと幅広く、当然、本書もたいへんに面白く、アイルランドのB&Bで夢中で読んだものだ。
私の旅の話ばかりで恐縮だが、あの時はまだ学生。
夏休みを利用して海外にでも行きたくなった。しかし当然、あまり所持金はない。
12万ばかりの往復航空券を買い、まずは北アイルランドのベルファストに降りた(ヒースロー経由)。
そこで自転車を買い、反時計回りにアイルランドを一周したのである。
ただ、8月とは言えど、アイルランドの天候はそんなにいつも明るいわけではない。
自転車に乗りながら、雨宿りできない長く続く道を、ひたすら雨に打たれながら走ったことも何度かある。
それだけに、今、手元にある本書(文庫本)は、雨に濡れて乾いてカピカピになっている。
とにかく本書の面白さを一言で言うのは難しい。
ただ、学者の書く文章だからと言って、近寄りがたいものではなく、むしろ文章が洒脱でありながら、豊富な知識、客観性、そして著者の思いがライトタッチに綴られている。
アイルランドものの本は何冊か読んだが、カラー写真がまったくないのだが、一気に読めて、知的興奮さえも得られるのだ。
実際、自転車で旅をしていて実感したのが、アイルランドの標識に不可解さである。
まず標識自体が小さい上に、英語とゲール語が混ざってて読みにくい。
そして一本の柱に、それらの小さな標識が東西南北を向いて刺さっている。
しかもその方向が道ではなく、もろに牧場を指している場合さえある。
自転車ならまだしも、自動車でこの標識を識別するのは至難の業であろう。
これはおそらく、妖精の国アイルランドだけに、「妖精」のための標識ではないかと、そんなユーモアさえものぞかせる。
とにかく本書は読み始めたが最後で、面白くてぐいぐいと時間のたつのを忘れて読んでしまう。
本書にも紹介されてあるが、丸山薫の詩に
「あいるらんどのやうな田舎に行かう」
というものがある。
「何でも見てやろう」の小田実はその詩をして、
「これを口ずさめば、誰だってアイルランドに行ってみたくなるではないか」
と述べているが、本書「アイルランド歴史紀行」を読んでも、同じことが言える。
今からすると20年前の本になるが、これからも永遠に色あせない、アイルランド旅行記の古典としての輝きが今でもある。
・この本を持ってもう一度アイルランドに行きたい
- アイルランド歴史紀行 (ちくま学芸文庫)/高橋 哲雄
- ¥1,050
- Amazon.co.jp
人生を変える100日ブログ :10日目